※となみ野とは、砺波市と南砺市の総称です。
となみ野の特産品
福光バット
国内でつくられる年間約30万本の木製バットの半分がロンウッドなどメーカー5社が集まる富山県南砺市の福光地区産といわれる。冬場の湿度が高く、材料となる生木から水分がゆっくりと蒸発していくため、木が割れにくいという「地の利」が福光にバット産業を根づかせた。

里芋
南砺市福野の焼野地区は古くから里芋作りが盛んです。享保5年(1720年)、加賀藩より種芋が譲渡され、栽培が始まったと文献より伝わっています。排水良好で肥沃な庄川の沖積土壌である福野の焼野地区に最適な作物として適応した里いもは、特産物として加賀藩に上納されているほどでした。以降300年、幾多の歴史的な困難を乗り越えて、昭和47年、ついに「国の産地指定」を受けました。現在においても、やわらかく粘りがあり、甘みのある「福野の里いも」として広く愛されております。

大門そうめん
砺波市大門地区で素麺作りが始まったのは、江戸時代の後期1848年からといわれています。「大門素麺」のルーツは石川県です。石川輪島市というと、その当時は素麺の生産地として栄えていました。
「大門素麺」は、ほとんどの工程が手作業で作られます。「大門素麺」作りは、寒さが厳しくなり、空気の乾燥する冬の時期に作られます。10月から翌年の3月にかけて作られます。質の良い小麦粉を使い、時間をかけて捏ねたものを一晩寝かせます。「大門素麺」は、その日の気温や湿度によって、塩水の量や熟成時間を変えて作られます。寝かせたものを板状に伸ばしてから、より合わせて細く長く伸ばしていきます。伸ばされた麺を「はさ」と呼ばれるさおにかけて、下の方をゆっくり引っ張っていき、さらに伸ばしていきます。このようにすることによって、よりコシが強い素麺にになり、美味しい「大門素麺」となります。「はさ」にかけて乾かされた素麺は、半乾きの状態で丸まげ状に手作業で丸められます。さらに乾燥させます。時間をかけて丁寧に作られた「大門素麺」は、コシの強い美味しい素麺に仕上がります。


庄川ゆず
日本最北のゆず栽培最適地ともいわれる砺波市庄川町金屋地域では古くより「金屋ゆず」の名で親しまれ栽培されてきました。表皮に凸凹があるので、外見の美しさには少々欠けますが、果肉が厚く、酸味の強さが特徴で、特有の香りも強いゆずです。ゆずの里ならではのイベントとして毎年11月中旬に、「庄川ゆずまつり」が開催されます。

五箇山豆腐
かつて秘境と呼ばれた五箇山地方には世界遺産や民謡などの文化遺産とともに独自の食文化が継承され今も息づいています。なかでも代表的なものが「五箇山とうふ」です。
奈良時代、中国より伝えられた豆腐は元々、堅豆腐でした。その後、日本で工夫を重ね柔らかい豆腐となったが、ここ五箇山では豆腐本来の姿がそのまま現代まで続いています。五箇山では江戸時代初期にすでにとうふ造りが始まっているとされ、当時は各家庭で「晴れの日のごちそう」として大切に造られてきました。
古来より伝わった独自の製法でつくられる伝統の味。その特徴は水気が少なく、縄でしばっても崩れないほど身がぎゅっと詰まった堅豆腐で、大豆本来の旨味、豆腐本来の姿をそのまま今日まで伝えています。

鮎
一級河川庄川の清流に育まれた鮎は、格別の味わいがあると喜ばれています。小ぶりですが、身がしまり食べたときの独特な香りは鮎の別名「香魚」にふさわしいものばかりです。
鮎は幅広い料理が堪能でき、炭火で焼いた「塩焼き」をはじめ珍味の「うるか」や「姿造り」、「酢の物」、「姿寿司」などが味わえます。

観光スポット
チューリップ公園
砺波市特産で市の花でもあるチューリップをテーマとした四季折々の花を楽しむことのできる都市公園。
トルコ調の「ヤロバの泉」から北門を抜けると7.0haの公園が広がり、春には600品種、100万本のチューリップが、夏には色鮮やかなカンナが咲き誇り、訪れる人々を楽しませます。また、毎年春の「となみチューリップフェア」、夏の「となみカンナフェスティバル」など様々なイベントも開催されます。
となみチューリップフェアは、300万本のチューリップが彩る国内最大級の花の祭典です。大花壇、花の大谷、水車苑、オランダ風花壇など、会場いっぱいに咲き誇り、様々なイベントも開催します 。
公園内外には日本最大級の五連水車やチューリップ四季彩館、美術館、郷土資料館、中嶋家などがあります。
五箇山合掌集落
五箇山は、富山県の南西端、庄川沿いに位置する自然豊かな地域です。立ち並ぶ合掌造りの建物、のどかな山村風景、どこか懐かしい小さな山里が点在します。その中で、相倉(あいのくら)集落と菅沼(すがぬま)集落が岐阜県白川郷荻町集落と一緒に1995年 「世界遺産」に登録されました。日本を代表する文化遺産に多くの方が訪れています。

井波別院瑞泉寺
井波別院瑞泉寺は、明徳元年(1390年)、本願寺5代綽如上人によって開かれました。この寺は、北陸の浄土真宗信仰の中心として多くの信者を集め、大きな勢力を持っていましたが、16世紀、佐々成政の軍勢に攻められ、焼き払われてしまいました。兵火を逃れて城端北野に移った後、再び井波へ戻り、現在の場所に再建されました。
現在の本堂は、明治18年(1885年)に再建されたもので、北陸地方の真宗木造建築の寺院としては、一番大きな建物です。棟梁は井波大工の松井角平恒広で、他の大工、井波の彫刻師が中心となって完成しました。
太子堂は、大正7年(1918年)、井波建築、井波彫刻、井波塗師の優れた技を集めて再建されました。棟梁は松井角平恒信で、大工134人が建築にあたり、7年がかりの大工事でした。
山門は、天明5年(1785年)、京都の大工によって建て始められましたが、京都本願寺の再建工事が始まったため、井波大工がその後を引き継ぎ完成しました。山門正面の梁の龍は、京都の彫刻師前川三四郎によって彫られたもので、明治12年(1879年)、瑞泉寺大火のとき、近くの傘松に登って水を吐いたので山門が焼け残ったという言い伝えがあります。また、正面中央の精ちな彫刻の多くが井波大工の力作で、井波彫刻の基となったものです。この山門は、県重要文化財に指定されています。
7月の太子伝会では、聖徳太子像の開扉と八幅の絵解きが行われます。井波彫刻発祥の地としても名高く、秀作逸品を建物の至る所に見ることができます。

伝統工芸
井波彫刻
日本一の彫刻の技術を誇る伝統的工芸品”井波彫刻”は、荒彫りから仕上げ彫りまで200本以上のノミ、彫刻刀を駆使する高度な技術を持っています。 井波彫刻の発祥は、1390年(明徳元年)に建立された井波別院瑞泉寺が何度も焼失し、その度井波の宮大工により再建されてきたことが大きく関わっています。宝暦・安永年間(1763年〜1774年)の瑞泉寺の再建には、御用彫刻師の前川三四郎が京都の本願寺より派遣されたことにより、井波の大工が師事し教えを被り、その後寺社彫刻の技法が、欄間や獅子頭、天神様(菅原道真)などの工芸品に派生し今日まで受け継がれています。また4年に一度「南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ」が開催されています。 2018年(平成30年)5月24日には、井波彫刻を核とした「宮大工の鑿(のみ)一丁から生まれた木彫刻美術館・井波」として日本遺産に認定されました。

五箇山和紙
その昔、四百年前の江戸時代、五箇山平地域で作った中折紙が、その当時の越中(富山県)を収めていた、加賀百万石二代藩主、前田利長公に贈られたという記録が残っています。
以来、五箇山和紙は加賀藩の手厚い保護を受けながら発展し、良質和紙の産地として今日に至っています。
山里の自然がはぐくんだ都の文化。五箇山和紙は、八尾和紙、蛭谷和紙とともに「越中和紙」の名で国の伝統的工芸品に指定されています。

三助焼
三助焼は砺波市において、150年にわたり焼き物を作り続けています。地元で取れる土を用い、この土地が生み出した草木から釉薬を作り、作陶をしております。
富山県砺波市の福山丘陵一帯は陶土に恵まれ、古くは奈良・平安時代の須恵器に始まり、生活用具と瓦の製造が行われていました。
この瓦製造の一軒であった谷口三助(嘉永元年~明治38年)とその長男、谷口太七郎(明治7年~昭和8年)が瓦製造の窯で壺、鉢、皿などの生活用具を作り始め、三助焼の基礎を築きました。

祭事・イベント
城端曳山祭
越中の小京都・城端の春を彩る、城端神明宮の祭礼。 300年の伝統を誇る優雅な祭り。 精緻な彫りと塗りが施され、御神像を乗せた6台の山車が町中を練り歩きます。 先頭に立つ獅子舞と剣鉾が悪霊を鎮め邪鬼を払い、続く傘鉾が神霊をお迎えします。その後を庵屋台の情緒あふれる庵唄、伝統の城端塗の粋を尽くした曳山が続きます。夕刻からは提灯山となり、日中とは違う風情を楽しめるのも魅力。

城端曳山祭
夜高
砺波地方を中心に伝承される祭の一つで、和紙と竹でできた夜高行燈を立て、田祭りや神事を行う。起源は南砺市福野にあり、福野開町の際に伊勢神宮からの分霊を迎えるにあたり、行燈を手に手に持って出迎えたのが由来で、現在も春季祭礼の神事として福野夜高祭が行われているが、砺波・南砺地方では6月初旬に、田植えが終わり休みを取るという意味の「ヤスンゴト」(休んごと)といわれる習慣があり、砺波夜高祭りと小矢部市の津沢夜高祭り、庄川観光祭(庄川夜高行燈)など各地で行われる夜高祭は、神事と異なりこの時期に合わせ各地で五穀豊穣 、豊年満作を願う田祭りとしておこなっているもので、福野から伝わったものと考えられる。



スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド
1991年(平成3年)4月に福野町(現 南砺市)の若者達がスキヤキ・ネットワークを立ち上げ、同年8月に世界各国おもにアフリカ・アジア・中南米のミュージシャン達による音楽紹介を通じて異文化交流を目的に初めて開催された。現在では毎年8月下旬の金曜日から日曜日の3日間に渡り南砺市福野文化創造センターヘリオスとその周辺で行なわれている。開催中は世界各国から招いたプロミュージシャンやアマチュアミュージシャンのライブステージが行なわれるほか、市内に滞在するミュージシャンが会場での各国の楽器演奏指導、楽器製作等多くのワークショップを開くなど、世界各国のミュージシャンと異国文化交流をはかる市民参加型フェスティバルとして続いている。なお開催期間前にも県内各地でミニコンサートや各種ワークショップを開いている。

音楽隊によるパレード

他にもまだまだ魅力があります。
詳しくは、各市の観光協会HPよりご覧ください。
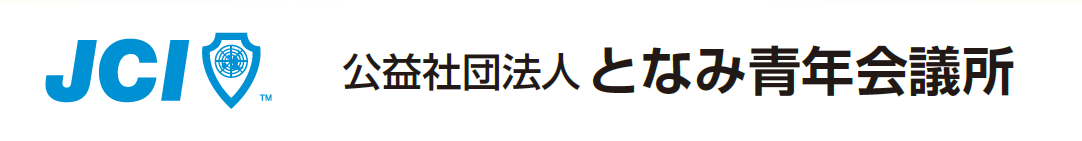

.png)


